こんばんは卵屋です。
評価シリーズ第7弾。評価シリーズの最後です。
これまでの流れを振り返る。
これまでの記事はこちらからどうぞ。
現役理学療法士が教える「評価」の流れと実際2(情報収集、検査測定、動作観察)
現役理学療法士が教える「評価」の流れと実際5(課題・アプローチ点抽出、ICFについて)
はじめに
今回は評価シリーズの最後、「治療プログラム立案」について解説する。
全体像を把握して、階層的に情報を整理して、各階層の課題を絞り込んだら、その課題を解決する方法を選択していくという流れになる。
治療プログラムは読んで字のごとく、本来は「評価」の先の「治療」のゾーンに入る項目。
あえて評価の中に置かれている理由は、
- 一通りした評価の総まとめ的な位置付けだから。
- 「治療と評価は一体」と言われるように治療によって得られる反応もまた評価になるといった考えがあるから。
- 何も考えず評価したんだから流れで治療も考えておこうよ的なノリで。
のどれかと推測している。
個人的には評価と治療は一旦切り離して考えるべきだと思っている。
その理由は①基底還元論に陥らないため、➁機能訓練をする際の短絡的な思考を回避するため、の2つ。
①基底還元論とは心身機能→活動→参加という流れでしか活動や参加を変えられない、つまり「心身機能が改善しない限り活動や参加は向上し得ない」とする考え方を言う。
評価と治療を一緒に考えすぎると機能訓練だけに目を向けてしまう恐れがあると危惧する。
(誤解のないように言っておくと、一方で機能制限に目を向け機能訓練に力を入れるのは理学療法士の本分。そこをおろそかにしてもよいという意味ではない。)
➁次に機能訓練をする際の考え方に目を向ける。
評価はあくまで「どうなっているか」の把握、治療は「どうすればよいか」の方法論。
ここが「評価」→「治療」と一直線につながらないケースが臨床ではままある。
一方、その方法だけですぐに改善してこないのもまたよく経験することだと思う。
「筋力が低下しているのだから筋力を向上させれば元通りに歩ける」が通用する世界ならば、「評価」→「治療」と直線的に問題点から治療法を選択すればよいが、実際には評価で問題点を絞った上で、そこからどうすればよいかをさらに深く考えていかなければならない。
しかし、そこには様々な理論や「思想」があり理学療法界で未だに統一した方法論は見つかっていない。
「いやいや、それは評価が未熟できちんと問題点を特定できていないからではないか」
「『筋力』という広いレベルの問題点で済ませずに『筋持久力』や『協調性』といった詳細な問題点まで突っ込んでいくべきだ」
この手の意見が聞こえてきそうだ。
確かに一理ある。が、そこに関してもこれまた完璧に分類できる方法論はない。どこまで言っても特定はできない。
何が言いたいかと言うと、評価によって細かなレベルの問題点を特定することもできないし、仮に見つける方法があったとしても「それ」を改善させる方法も見つかっていない。
今のところ最も最善の方法は、なるべく妥当性の高い評価方法を選択して、なるべく妥当性の高い治療法を選択するしかない。
つまり評価の知識と治療の知識は別々に存在するということが言いたい。
冒頭でも言った通り評価はあくまで「どうなっているか」の話、治療はそこから先の「どうすればよいか」の話になるので、一旦距離を置いて考えるべきだと私は主張する。
はてさて、困った。「治療」について述べようと思うとこんなもんじゃ足りないくらい長い長い解説が必要になりそうだ。うむ、とても1記事ではまとめきれない。
よし、今回は普段私が臨床で治療プログラムを組む際に意識しているポイントについて解説をしていくことにしよう。それで勘弁してください。
治療プログラム立案のときに意識するポイント
階層性
毎度おなじみで聞き飽きたかもしれないが「階層性」。やっぱりこれははずせない。ここ3年くらい連続で受賞している「エビデンス」に続く今年の流行語大賞理学療法部門にノミネートしていただきたい。
評価シリーズで幾度となく出てきたこの言葉。治療プログラムにおいても重要だと主張する。
一般的に治療プログラム立案とは、ICFの「心身機能・身体構造」にアプローチし「活動」に反映させることを目的にプログラムを考えることを言う。
例えば「膝関節伸展筋の筋力低下により歩行時に膝折れが起きている」と評価した場合は、「じゃあ膝関節伸展筋が発揮できるよう強化して歩行の安定性を向上させよう」といった具合。
この流れ自体に大きな問題はないが、私はこれをあくまでも狭義の意味での「治療」と捉えている。
一方、「治療」というものを広義に捉えた場合、理学療法士が患者さんのために行う全ての関わりを指すと考えている。
これらの関わりも広く捉えたときには全て理学療法士の「治療」と考えるべきだと思っている。
このように、ICFで課題を抽出し、心身機能・身体構造に対する治療プログラムを立てつつも、相対的独立性を利用して各階層に直接的にアプローチしていく意識を理学療法士は持つべきであると考える。
運動量
入院中(特に回復期病棟)の患者さんを前にして理学療法士が最も恐れなければならないものは「廃用症候群」である。
入院生活というものは思っている以上に動いていない。
患者さんは少し入院するだけですぐに足の筋力は落ち、いともたやすく歩けなくなる。
それを防ぐことを一番期待されている職種が理学療法士で、医師が「リハビリ」をオーダーする目的のほとんどは「リスクを管理した上で運動させてくれ」なのである。アライメントだとか筋緊張だとか小難しいことはさておき、シンプルに運動する機会をたくさん作ることが求められていると言える。
ゆえに一日の運動量がトータルでどれくらいかというものは常に意識しながらプログラムを立てる必要がある。
一日中部屋にこもってリハビリの時にしか運動する機会がない患者さんと、病棟をウロウロと歩き回っている患者さんとでは、マンツーマンで関わるときのプログラムも変わってくる。
1日の運動量が少ない患者さんには「量」に重きを置いたリハビリを、1日の運動量が多い患者さんには「質」に重きを置いたリハビリを行うといった具合で、運動量をベースに自身の重きを置く部分を変化させることが必要である。
「リハビリでマッサージしてくれたら疲れとれるからまた自分で歩く練習できるわ」と言われれば私は喜んでマッサージをする。
常に1日の運動量を意識してプログラムを変化させている。
「ルーティン」と「日替わり」
狭義(心身機能→活動レベル)の治療の話に移る。
プログラムを立てる際は、ある程度「ルーティンで行うプログラム」と「日によって変えるプログラム」を意識して立てている。
ルーティンプログラム
ルーティンプログラムには、①誰に対しても基本的に実施するプログラムと、➁評価した結果基本毎回実施するプログラムとがある。
「マッサージ」については色々な意見があり目的や理由を述べると長くなるのでここでは避ける(いつかまとめて記事にします)。
「起立・着座運動」「歩行練習」については運動量を確保し廃用症候群を予防することが大きな目的。また日々の体調の変化やざっくりとした評価のため。
「〇〇を獲得するために―」や「退院後の〇〇を見据えて―」といった深い考えを持って実施する訳ではなく、「とりあえず立ち座り」「とりあえず歩行練習」に近い感覚で実施している。
運動しなければ弱っていくという一般的な事実に抵抗するために実施する運動。これらは誰に対しても基本的に実施するルーティンプログラムである。
これらを毎回実施する理由は、ある程度の期間をかけて頻回に実施しないと効果が少ないと考えているため。
また痛みの程度など日単位で状態を確認しながら調節していきたいプログラムであるため。「1回だけ目一杯やってそれで終了」とはなりにくい訓練である。
このようにある程度毎日ルーティンで実施するプログラムをまず考える。
(ちなみにルーティンプログラムも2週間程度で見直す。ルーティンとは言え2週間程度の経過を見て効果を判定し必要に応じて変更する。)
日替わりプログラム
一方で毎日毎日ずっと同じことをしているわけではない。上記のようなルーティンプログラムをベースにしながら、日によってコロコロ変えるプログラムもある。
といった具合に、時期や身体機能によって患者さんに合わせたプログラムを日によって変えながら実施していく。
このようにルーティンと日替わりを組み合わせてプログラムを組んでいく。
ルーティンと日替わりの配分
あくまでも私の例だが、「ルーティン:日替わり=2:1」程度の配分で実施することが多い。
60分であれば、40分ルーティンプログラム、20分個別プログラムといった具合で、個別プログラムの配分はあまり多くない(あまりコロコロとプログラムを変えない)。
当然この辺りは時期や患者さんの状態によって変化することは言うまでもない。
さらにどの病期(急性期、回復期、在宅など)に関わっているかによっても大きく変わる。
まとめ
さて、今回は治療プログラム立案を行う際に意識するポイントについて完全なる独断と偏見で解説を試みた。
治療の領域は理学療法士によって重きを置く理論が違い、なかなか統一した方法が得られないくいのが現状であり、いにしえから続く理学療法界の課題である。
私が大事にしている理論などもどこかで記事にできればと考えている。
さて、これで現役理学療法士が教える評価の流れと実際シリーズは終了。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。

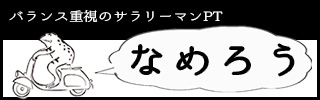







コメント