こんばんは、卵屋です。
シリーズ「運動学習」、第3弾。
前回は運動学習と運動制御との関係について解説した。
今回は主要な運動制御理論について紹介し、いつものように私見を述べていく。
これまでの記事はこちらからどうぞ
現役理学療法士が「運動学習」について語る1
現役理学療法士が「運動学習」について語る2
また、これらの記事は以下の書籍にかなり強く影響を受けている。
深く学びたい方はぜひ手に取って学習することをおすすめする。
運動制御理論
さて、ここからはリハビリテーション界に大きな影響を与えた主要な運動制御理論について触れ、私なりに噛み砕いて解説してみようと思う。
反射理論
という理論である。
ここでいう反射とは入力された刺激に対して機械的に反応を返すことを指す。
反射理論では、立つも、歩くも、立ち止まるも、手を伸ばすも全て「反射」による反応だと主張する。
うん、かなり無理がある理論だ。
人間の意思や意図、脳でのコントロールといったものを全て無視した理論だと言える。
「反射」というものがあるというのは分かるが「全ての運動がそれで成り立っている」はいくらなんでも「そんなはずはないだろう」とツッコまざるを得ない。
それでも昔はこの理論をベースに治療が展開されたと言うから驚きだ。
科学が進歩してそんなことはありえないと分かりきっている時代に生まれたからそう思うのか、これを信じていた治療家たちはこの不思議な理論に異を唱えなかったのだろうか…。
階層理論
と主張する理論である。
これだと先ほどの反射理論と違い高次の脳も対象に入るため意図的な動きの説明もできる。
この理論では下位になるほど「反射」が利用され、上位の階層はそれら反射中枢を制御していると主張する。
例えば「立つ」という動作は上位(高次連合野)が中位(運動野)に指令を送り、脊髄レベルまで指令が行くと、中位は下位(脊髄レベル)の反射を利用し筋肉を働かせる、その結果筋が働き「立つ」という動きが遂行されるといった具合である。
さらに、脳卒中で合目的な運動が阻害されるのは上位の制御を失った下位の反射が出現するからと主張する。
この理論をベースにした治療法、治療概念で最も有名なところで言えば間違いなく「ボバース」だろう。そう、階層理論は今なお多くの理学療法士に強く支持されている。
何を隠そう私はボバースには否定的だし勘違いボバース信者は大嫌いだが、階層理論自体には一定の真実が隠されていると思っている。
神経系の上位が下位を制御しているという事実は多くの場面でそうだと思う。
トップダウン的に制御する過程は確かに存在すると思うし、私もそれを狙って課題の設定やフィードバックをすることもある。
Swayne ら(2008)は、脳卒中の急性期の回復メカニズムは残存している皮質脊髄路を刺激してその興奮性を高めることで麻痺の回復を促進する時期で3ヶ月までに消失し(1st stage recovery)、次のステージは皮質間の新しいネットワークの興奮性に依拠する時期で6ヶ月までに消失する(2nd stage recovery)、それ以降はシナプス伝達の効率化による回復であるとした(3rd stage recovery)。
このステージ理論は、臨床での経験ともかなり合致する。6ヶ月程度までに完成された様々な動作は、それ以降にトレーニングをして「動作自体(例えば歩行やトイレ)」を獲得(自立)することは出来ても、「動作パターン(例えばぶん回し歩行など)」を修正することは困難を極める。
脳卒中発症から半年程度までに獲得した動作パターンを、その後いくら練習しても簡単に変えられない事実は、中枢での指揮系統が下位をコントロールしている仮説を一定の範囲で支持していると思う。
私もこれらの理由から、発症から3ヶ月頃までのリハビリは「慎重に」プログラムを組むようにしている。
中には代償を「悪」とし、正しい運動パターン・運動感覚だけに焦点を当てる考え方もあるくらいだ(ボバースや認知運動療法など)。
そこまで極端に偏らなくても、ある程度麻痺側をしっかりと使っていく、参加させていく意識は持つべきだと思っている(ちなみに私は「効率の良い代償動作の獲得」が目指すべき目標だと思っている)。
少し話がそれたが、階層理論は運動制御を完璧に説明できる理論ではないかもしれないが、一方で多くの真実をついている理論だと思っている。
一方で、問題なのは「トップダウン制御だけ」としている点。
厳密なトップダウンのみを主張するのはやはり無理がある。
階層理論で説明できない現象として、例えばCPGといった脊髄レベルでの神経回路網の存在が明らかになっている。上位との連絡が切り離された脊髄レベルの神経回路だけでも歩行に近い動きが可能な事実を階層理論では説明できない。また健常な人においても逃避反射など上位の連絡を待たずして起こる運動もある。
階層理論の「全てがトップダウンで」という主張には説明できない様々な課題がある。
プログラム理論
この理論には大きく二つの重要な概念がある。
➁抽象化運動プログラムという概念
➀の中枢性運動パターンは「概念」というより「実体」として存在するものとされている。
先にも出たCPGは脳が一つ一つの筋肉に指令を与えるのではなく脊髄レベルの神経回路網により筋肉を働かせるというもの。階層理論との違いは上位からの指令がなくても運動が実現される点。下位からの刺激は運動を惹起するのに必須ではないが、調整するのに重要な役割を担っているとしている。
つまりプログラム理論では完全な脳からのトップダウン制御ではなく運動発現のための中枢が分散して存在し、それぞれ運動の制御に関わっていると説いている。
➁は「スキーマ理論」に出てくるGMPのこと。スキーマ理論はSchmidtによって提唱された運動制御と運動学習を統合させた理論。どちらかというと運動学習の理論として扱われることが多いが、運動制御とセットの理論であることは間違いない。
突然だが、スキーマ理論は素晴らしい。これほど完成度の高い理論は他にない。実によく出来た理論だと思う。
スキーマ理論は心理学領域から発展した理論である。
すなわち神経系のどこそこが運動制御・運動学習の何に関わっていて、運動するとき・学習するときにどこの神経がどう変化して…といった生理学的な話は置いといて、たくさんの動物や人に何か課題を与えて、たくさんの返ってきた結果を分析して考察、その結果こう考えると最も辻褄が合うんじゃね?といった手法で作り上げる理論なのである。
スキーマ理論を解説しようと思うと図が必須になる。
原著の図より、日本語に訳されかつ分かりやすいように改変しや大橋ゆかり先生の図と解説が最も分かりやすい。著作権の関係上それらを引用することは出来ないため詳しく知りたい方は是非以下の書籍を手に取って学習していただきたい。
ここではスキーマ理論を構成する主要な用語と大枠だけ簡単に説明する。
ある一つの「目的とする結果」(例えばホームランを打つ)が決まったらそれに合わせて身体を動かさなければならず、そのときに必要なのが「パラメーター」である。理想とする結果を得るために筋肉の働かせ方や力の入れ具合を具体的に決めてあげる必要がある。これは過去の経験から作られ記憶されていく。
この、ある運動を行ったことによって生じた結果と、その運動を行う際に使用した運動のパラメーターの関係を「スキーマ」と呼ぶ。
つまり、Schmidtは人はGMPとスキーマ(再生スキーマと再認スキーマ)によって運動を制御しており、それらの精度を上げることが「運動学習」であるとした。
これは前回の記事のBerenstain問題の一つの解法でもある。
自由度問題(脳が一つ一つの筋肉に指令を出すと考える鍵盤支配型モデル、数千万・億の組み合わせの中からたった一つを選択してスムーズな運動を発現させるのは、いくら優秀な演奏者(脳)がいても不可能なんじゃないか?またそれらを学習して保持しようと思うと記憶を留めておく容量がどう考えても足りないんじゃないか?という問い)に、GMPとスキーマという解をもって闘いを挑んだわけだ。
すなわち脳が一つ一つの筋肉に指令を送らずとも、GMPを呼び起こして目的とする結果のスキーマを入れ込むだけで脳がやる作業を劇的に減らせると主張したわけだ。GMPやスキーマはある種のプログラムで少ないクリック数でそれらを動かせるというのがプログラム理論と呼ばれる所以である。
システム理論
私の知る限り、システム理論を調べても「システム理論とは〇〇という理論だ」と一言で表している書籍、記事などはない。
なので説明がとても難しい…。
Berenstain問題を提起したNicolai Berenstainは、以下のように考えた。
(Anne Shumway‐Cook , Marjorie H. Woollacott (2009). モーターコントロール―運動制御の理論から臨床実践へ 医歯薬出版)
う~ん、よく分からん。システム理論については調べれば調べるほど何が言いたいかがよく分からなくなる。
強引に私なりに解釈すると、
と主張しているように感じる。
これは自由度問題を解決したいという意思を強く感じる。
すなわち、システム理論以前に考えられていた運動制御理論、「脳が数千万・億といった自由度の中からたった一つの組み合わせだけ瞬時に選んで運動を実現している」という前提を否定し、環境(を含めたこの世界の秩序)によってある程度勝手にもたらされた要因をうまく利用しているのではないか、それによって脳側が制御しなければならない自由度の数を極端に減らしているのではないか、とする考え方。
そしてそう考えると、そもそも環境側のしていることを理解せずに脳側を理解することは難しいんじゃね?という主張ではないかと私は解釈している(詳しい方は是非教えてください)。
さて、システム理論では、どの書籍にも以下のような項目が解説の軸となっている。
水を温めたときの対流とか、雲の形成パターンといった物理・化学的な現象、ホタルの光の同期現象といった生物的現象、みたいなものが運動制御の領域にもあるんじゃないか、という考え方。それを数学的に求め法則として明らかにすれば、この部分は「勝手に」世界がしてくれていることで、それ以外の要素を脳が制御すれば自由度問題の解決につながるんじゃね?という寸法。
スキーマ理論ではスキーマ関数というものを使い入力と出力の関係を説明した。例えばボールを投げる運動について、リリースの瞬間の手首の屈曲スピードとボールの速度は比例関係にあり、屈曲スピード(入力)が速いほどボールのスピード(出力)も速くなる。このような運動は入力と出力の関係について直線的なグラフが描ける。
しかし、例えば馬のウォーク、トロット、ギャロップとスピードによって走り方(歩き方)が変わる現象は、スピード(入力)と歩き方(出力)とを直線的なグラフで結ぶことはできない。あるスピードをきっかけにウォークからトロットに変化し、またあるスピードをきっかけにギャロップに切り替わるといった具合で非線形的に変化していく。このような特徴を非線形特性という。この切り替わるきっかけとなる要素(馬の例で言うとスピード)やそのパラメーターが法則的に明らかになれば運動制御を解き明かす、あるいは運動学習につながるヒントになるんじゃね?という寸法だ。
動作として「安定していること(常に同じふるまいであること)」や「不安定(エラー)」を概念的にどう捉えるかの話に繋がるが、システム理論の中では「不安定」を必ずしも悪と捉えない。むしろ次のアトラクターのフェイズに移るための臨界ゆらぎであれば、新しい動きを獲得するために必要な要素と捉える。
以上、このような特徴からシステム理論は構成される。
う~ん、結局なんだかよく分からん、となったはずである。
それもそのはず、システム理論はどちらかという「運動制御」に強く寄った理論。我々が知りたい「運動学習」に応用しにくい理論なのである。要は「それが分かって何になるの?」「どう応用したらいいの?」という疑問が出てきてしまう。
「自己組織化」という概念をストレートに受け取ってしまうと、理学療法士が何をしようがしまいが、必要なシステムが「勝手に」集まって運動を実現してくれるんでしょ?となってしまう。
臨床にどう応用するかが分かりにくいことが個人的にシステム理論にのめり込めない大きな理由の一つである。
まとめ
今回は運動制御の理論について解説し私見を述べた。
個人的には今のところスキーマ理論が最も優れた運動制御、かつ運動学習の理論だと思っている。
そう、我々が最も知りたいのは「なんでそうなっているか?」よりも「どうすればよいか?」なのである。それはすなわち運動学習の理論なのである。
一方でシステム理論が無用の長物かというとそれは言い過ぎで臨床におけるたくさんのヒントを与えてくれる理論だと思っている。
前置きが長くなったが、次回からは運動学習について解説していく。
お楽しみに。
続きの記事→現役理学療法士が「運動学習」について語る4

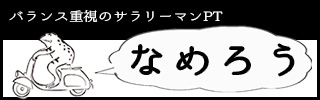



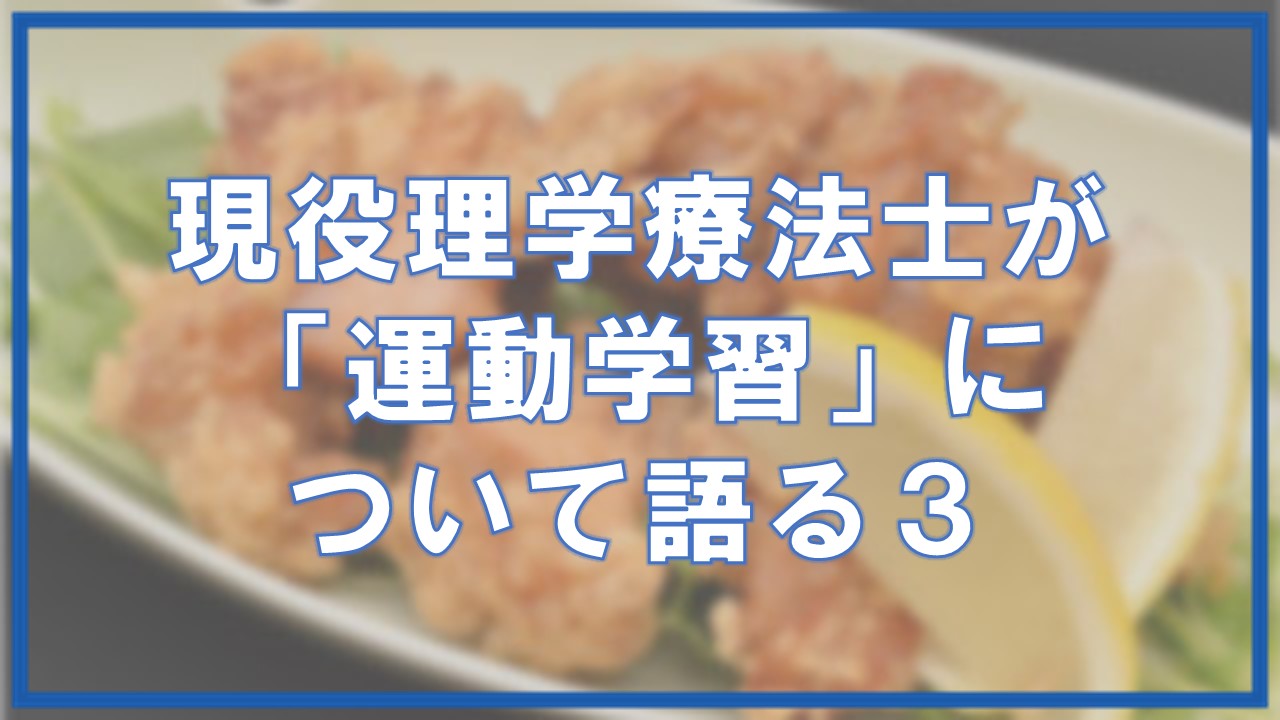




コメント