理学療法界隈を歩けば、決まって耳にする念仏がある。
「昔の実習は厳しかった」
というアレだ。
生き証人としてその地獄を闊歩した老兵もいれば、令和のホワイトな養成課程で育った若手は「どうせ年寄りの盛った話だろう」と冷めた視線を送っている。
果たしてあの狂騒の日々は虚飾か、あるいは凄惨な事実か。
ここでは、今や絶滅危惧種となった「かつての実習」の真実を、カルテをめくるように淡々と書き記していくことにしよう。
「昔の実習は厳しかった」
「先生、お疲れ様です。……お先に失礼します」
時計の針はとうに二十二時を回っている。病院の裏口、夜間通用口を開く瞬間の冷たい夜気だけが、麻痺した脳をかろうじて現世に繋ぎ止めてくれる。
これが理学療法士を目指す学生が必ず通る「臨床実習」という名の通過儀礼だ。
「リハビリテーション」という美名の下に行われる教育の現場を眺めると、そこには一種の狂気と、前時代的な徒弟制度の薫りが強く漂っていることに気づかされる。
バイザーという名の絶対君主
実習生にとって、指導者(バイザー)は神に等しい。
彼らの一挙手一投足、あるいは吐き出されるため息一つで、学生の明日の生存権が決まる。
「君、さっきの歩行観察でみえたことを教えて」
バイザーの低い声がリハビリ室に響く。
学生は脳卒中片麻痺患者のわずかな骨盤の傾斜や足関節の背屈不全など、昨晩必死に調べた知識を総動員して答える。
しかし、返ってくるのは正解ではない。
「…ふうん。まあいいや。明日までにもう一度教科書をみながらレポートにまとめてきて」
「明日まで」という言葉の絶望感。
それは、今日という日がまだ終わっていないことを意味し、かつ、明日という日が睡眠なしで訪れることを宣告する死刑執行書に近い。
デイリーノートという名の怨敵
理学療法士の実習を象徴するのは、何といっても「デイリーノート」と「ケースレポート」だ。
学生たちは、自身の一日の予定、患者の一日の変化・バイタル・動作分析、そして自身の考察を気の遠くなるような分量で書き連ねる。
医学という学問は、本来、客観的なデータの積み重ねであるはずだ。
しかし、実習におけるレポートは多分に「誠意の証明」という側面を持っている。
動作分析。 左の遊脚期はどんな様子だったか?なぜ左の立脚中期で膝が折れるのか?--わずかな観察時間、それも数時間前に見た現象を、さも今見ているかのように思い出しながら書き記さなければならない。
統合と解釈。 検査結果を並べるだけでは許されない。そこにある「心」や「生活」を読み解けと迫られる。
深夜二時。パソコンのブルーライトに照らされた学生の顔は、皮肉にも彼らが担当するどの患者よりも血色が悪い。
一日の睡眠時間は二、三時間。この極限状態で行われる「思考」にどれほどの臨床的価値があるのか。それは誰も問うてはいけないタブーなのだ。
コミュニケーションという名の断崖
リハビリテーションの本質は、人と人との対話である。
だが、実習生はこの「対話」に最も苦しむ。
患者は人生の途上で「動けなくなる」という絶望を味わった人々だ。そこに、知識も経験もない、ただ緊張で震えているだけの若者が放り込まれる。
「リハビリ、頑張りましょうね」
その一言がどれほど空虚に響くか。
患者から「あんた、学生さん? 練習台にされるのはごめんだよ」と拒絶された時、学生の心は折れる。
医療とは技術以前に「信頼」という名の目に見えない契約の上に成り立っているからだ。その契約書にサインをもらえないまま、実習という時間は無情に過ぎていく。
「フィードバック」という名の裁き
夕方、リハビリ室の電気が消え残務処理に追われるスタッフのタイピング音だけが響く頃。
それは実習生にとって、一日のうちで最も胃がキリキリと痛む時間の始まりだ。
「何か質問はある?」
バイザーから投げかけられるこの一言は、純粋な問いではない。それは学生の『熱意』を検品するためのリトマス試験紙であり、同時に、経験不足という『罪』をあぶり出すための拷問器具でもあった。沈黙すれば「意欲なし」という烙印を押され、浅薄な質問をすれば「勉強不足」と斬り捨てられる。
「なぜ、その筋力テスト(MMT)が必要だと思ったの?」
「……歩行の安定性を確認するためです…」
「で、その結果から何が言えるの?」
「……中殿筋の筋力低下が……」
「で、それがどう患者の生活に繋がるのか聞いてるわけ」
答えがバイザーの脳内にある「正解」に辿り着くまでこの問答は終わらない。
連日の不眠と叱責は、学生の精神を潤滑を失った関節のように、一歩ごとに軋ませすり減らしていく。
症例発表という名の「処刑台」
実習の最終日、一人の患者を深く掘り下げた症例について発表会が開催される。
これは数週間にわたる不眠不休の集大成であり、同時に公開処刑の場でもある。
数十枚に及ぶレジュメを、スタッフ全員分用意する。一文字の誤字脱字も許されない。
徹夜で印刷しホチキスで止めたその紙束が、発表開始数分で「論理が破綻している」と一蹴され、机の隅に追いやられる。
バイザー以外のセラピストからも容赦ないツッコミが飛ぶ。
「君の治療で、この患者さんは本当に幸せになれるの?」
もはや医学的検証を超えた哲学的な問い。
震える声で絞り出した答えが空虚に響く中、学生は悟るのだ。
理学療法士という人種がいかに陰湿で意地悪な生き物なのかを。
閉ざされた「反省会」のあとで
実習終了時、評価表を手渡される。
そこには、数字で記された「能力」と、辛辣な言葉で埋め尽くされた「所見」がある。
「合格」の二文字を勝ち取ったとしても解放感に浸る余裕などない。
病院の裏口を抜けた瞬間、夜風に吹かれながら学生が思うのは達成感ではない。
「二度とここへは戻りたくない」という、根源的な恐怖に近い拒絶反応だ。
戦場の出口、日常への帰還
「ありがとうございました。……お世話になりました」
学生は真っ黒なクマを作った目でバイザーに深く頭を下げる。
あれほど憎かったバイザーから「まあ、頑張れよ」と無造作に肩を叩かれると、不覚にも涙がこぼれそうになる。
病院の裏口を出る。
肺の奥まで吸い込んだ夜気は、リハ室の消毒液の匂いをゆっくりと、しかし確実に上書きしていく。
駅へと続く緩やかな坂道を下りながら、何度も何度も後ろを振り返りそうになった。
そこには、学生が置いてきた「未熟な自分」がまだ立ち尽くしているような気がしたからだ。
家に着いたらまず何をしようか。 泥のように眠るか。それともこの一ヶ月禁じていた酒を煽るか。
結局、学生は駅前のコンビニで一番安いストロング缶を一つ買った。
プルタブを開ける乾いた音。それが若者が捧げた数千時間の睡眠と自尊心に対する、世界からの唯一の返答であり、学生の「戦い」のささやかな終止符だった。
亡霊たちは語る
現代の視点から見れば、これらは明白な「教育の失敗」でありただの虐待に映るだろう。
実際、この過程で多くの才能が、開花する前に摘み取られていった。
今の学生がこれを読めば鼻で笑うかもしれない。
だが、当時の学生たちはその不条理を「理学療法士になるための通過儀礼」として飲み込むしかなかったのだ。
今の臨床実習は時間管理が徹底され、ハラスメントの通報窓口まで完備されていると聞く。結構なことだ。
教育が「根性論」から「システム」へと進化した証左だろう。
しかし、あの地獄を生き残った連中は酒が入ると決まってこうこぼす。
「あの頃は無茶苦茶だったが、死ぬ気で考えたあの時間が今の俺を作っている」と。
それは生存者ゆえの傲慢か、あるいはストックホルム症候群の成れの果てか。
真実は、今も臨床の現場で古びたゴニオメーターを回し続けるベテランたちの皺の刻まれた手の内にある。

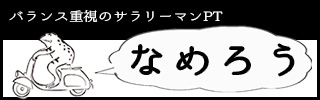





コメント